21歳ルポライター みく
皆さんこんにちは。フリーランスライターの「みく」です。
実は先日、友人と近所の神社に行った時のこと。一緒にお参りをしていたら、外国人観光客の団体が入ってきて、女性が手水舎の水をペットボトルに汲み始めたんです。私と友人は「え?」と顔を見合わせました。そして別の男性が鳥居にぶら下がってピースサインで写真を撮り始めた時、神社の方がかけよって制止する場面も目の当たりにしました。

帰り道、友人と「最近こういうの増えてるよね」と話していて、ふと思ったんです。これって一体なんなんだろう?単に「マナーが悪い」で片付けていいのか?もっと深い問題があるんじゃないか?
というわけで今回は、最近話題になっている「インバウンド観光客による神社での不敬行為」について、徹底的に調べてみました。これは単なるゴシップネタではなく、文化の衝突という普遍的な問題です。一緒に考えていきましょう。
Part 1:目を疑う…!神域で今、本当に起きている「不敬行為」の実態
まず、実際に何が起きているのか。ニュースになっているのは氷山の一角で、全国の神社から報告されている事例はもっと多いんです。
友人の神職さんに聞いたところ、おみくじ箱を「ガチャ」のように何度も振り回して遊ぶ人、手水舎で口をすすいだり水を飲んだりする人、さらには神聖な場所での不適切な撮影など、様々な行為があるそうです。
私が特に驚いたのは、賽銭箱に投げ入れた後、何度も何度も手を叩いて願い事をする人が多いということ。神道の作法では二拝二拍手一拝が基本なのに、「回数が多いほど願いが叶う」と勘違いしている人もいるそうです。
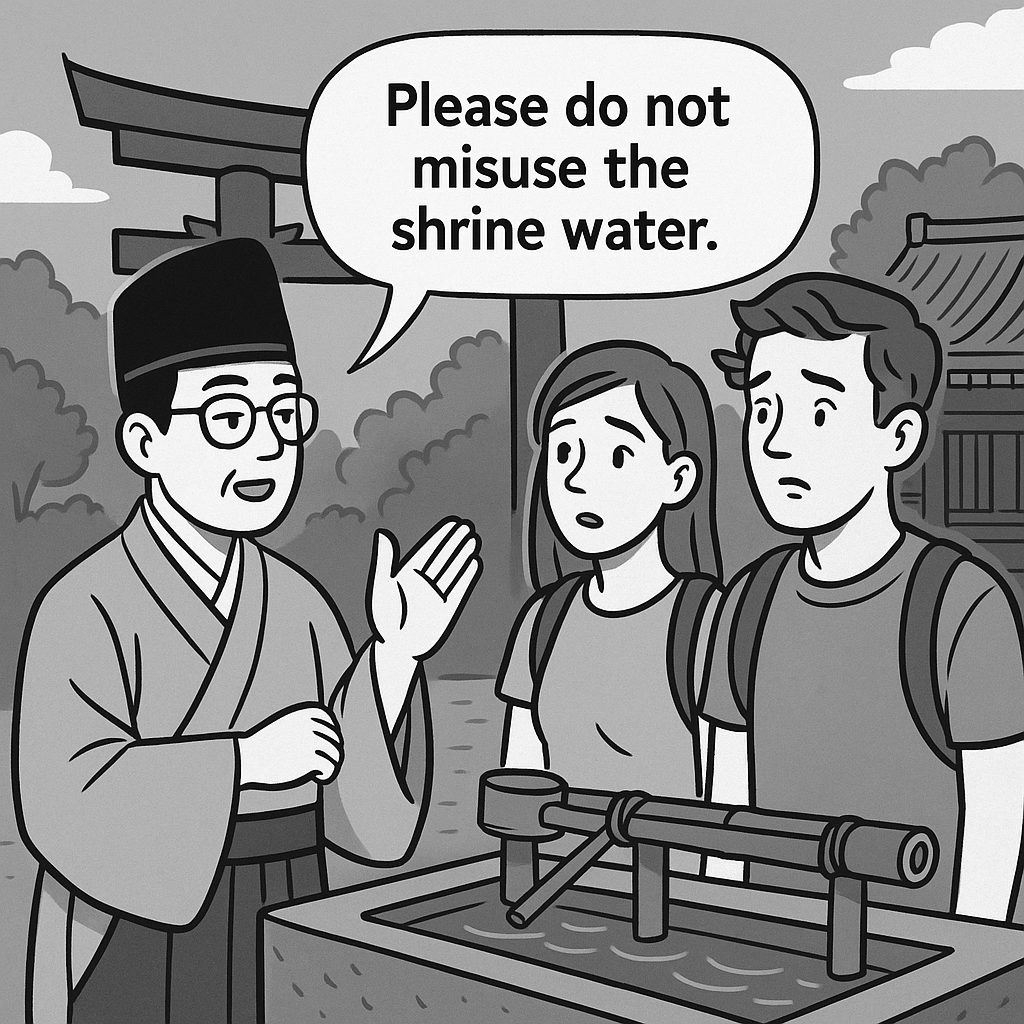
「一度、見回りをしていたら、おみくじの束を振り回して『ガチャガチャみたい!』と言いながら楽しんでいる若い外国人カップルがいて…」と教えてくれた神職さんの表情が忘れられません。おみくじは神様からのメッセージなのに、単なる遊び道具として扱われている現実に、心を痛めていました。
どんな行為が「不敬」とされているの?
神社での不敬行為を表にまとめました。これを見ると、単なる「うっかりミス」では済まされない行為が多いことが分かります。
表1:神社での主な「不敬行為」とその問題点
| 行為の具体例 | なぜ問題(不敬)なのか? | 特に注意すべき場所・モノ | 考えられる背景(一例) |
|---|---|---|---|
| ① 手水舎での不適切行為<br>(水遊び、飲用、ペット利用) | 手水は心身を清める神聖な儀式。作法を無視した行為は、神様への敬意を欠き、衛生面でも問題。他の参拝者にも不快感を与える。 | 手水舎(ちょうずや) | 作法を知らない、単なる水場と認識、好奇心 |
| ② 賽銭箱への不適切行為<br>(賽銭泥棒、異物混入) | 賽銭は感謝や祈りの表現。盗むのは犯罪。ゴミなどを入れる行為は、神様と他の参拝者の気持ちを踏みにじる冒涜行為。 | 賽銭箱 | 金銭目的(窃盗)、悪意あるイタズラ、文化・宗教観の違い |
| ③ 境内でのマナー違反<br>(大声、飲食、喫煙、ゴミ放置) | 神社は静寂と祈りの場。騒音や飲食・喫煙(指定場所以外)は場の雰囲気を壊し、他の参拝者の迷惑になる。ゴミの放置は景観を損ね、不敬。 | 境内全般、特に拝殿周辺 | 公共空間の認識違い、自国の習慣との混同、配慮不足 |
| ④ 立入禁止区域への侵入 | 神聖な場所や危険な場所への立ち入りは、神社の尊厳を傷つけ、安全上のリスクもある。文化財保護の観点からも問題。 | 本殿裏、神域とされる森、社務所裏 | 撮影スポット探し、好奇心、禁止表示の無視・不理解 |
| ⑤ 建造物・自然物への損壊<br>(落書き、破壊、木登り) | 歴史的建造物やご神木は信仰の対象であり文化財。傷つける行為は、神社の歴史と信仰を踏みにじる破壊行為であり、法的に罰せられる可能性も。 | 建物、鳥居、ご神木、石碑など | 記念のつもり、破壊衝動、文化財への認識不足 |
| ⑥ 過度・不適切な撮影/SNS投稿<br>(儀式撮影、迷惑ポーズ) | 祈りの場での無遠慮な撮影はプライバシー侵害や信仰妨害になり得る。不適切なポーズや場所での撮影・投稿は、神社の尊厳を貶め、誤ったイメージを拡散する。 | 拝殿内部、祈祷中、他の参拝者 | SNSでの「いいね」目的(承認欲求)、単なる記念撮影の意識、プライバシー意識の欠如 |
| ⑦ おみくじ・お守りの不適切扱い<br>(箱を揺らす、散乱) | おみくじやお守りは神様からのメッセージやご加護をいただくもの。おもちゃのように扱ったり、粗末にしたりするのは、神意を軽んじる行為。 | おみくじ授与所、お守り授与所 | 神聖なものという認識不足、好奇心、面白半分 |
| ⑧ 鳥居での不適切行為<br>(ぶら下がる、登る、ダンス) | 鳥居は神域への入口を示す神聖な門。物理的に損壊させるリスクに加え、神域への敬意を欠く象徴的な行為。神社の象徴を踏みにじる行為と受け止められる。 | 鳥居 | 単なる門や撮影オブジェと認識、悪ふざけ、SNSでの注目目的 |
私は、これをまとめながら、何度も心が重くなりました。神社は日本文化の宝であり、心のよりどころです。それを傷つけられるのは、本当に悲しいことです。
Part 2:「もう限界…」板挟みで苦悩する神社の声
取材を続けるなかで、ある神社の神職さんが打ち明けてくれた本音が忘れられません。
「正直、もうどうしたらいいか分からないんです。注意しても言葉が通じなかったり、逆に怒られたり。でも放っておくわけにもいかない。神様に対しても、私たちの先祖に対しても申し訳ない気持ちになります」
これは、単に「マナーが悪い」という問題ではなく、神聖な場所の「尊厳」に関わる深刻な問題なんです。
特に小規模な神社では、対応するスタッフも少なく、多言語対応も難しい。インバウンド観光客の増加を歓迎しつつも、神社としての本質を守りたい。そんな板挟み状態に多くの神社が置かれています。
「昔から地域の人に大切にされてきた神社です。でも最近は、写真を撮りに来るだけの人や、マナーを知らない人が増えて…。地元の方から『神社が観光客を呼んでいるせいで落ち着かなくなった』と言われると、本当に胸が痛みます」
神社関係者の苦悩は、想像以上に深いものでした。

「観光客は増えたけど、心が置き去りにされてる」って、神職さんの言葉が胸に刺さった…。神社って、ただの観光スポットじゃないんだよね…。
Part 3:「不敬行為」が生まれるメカニズム
では、なぜこのような問題が起きるのでしょうか?
異文化理解の難しさ
最も大きいのは文化的背景の違いです。例えば、自然物に神が宿るという考え方は、一神教の文化圏の人にとっては理解しづらいかもしれません。
私が留学していた時、友人から「日本人は木や石にも神様がいると思ってるの?それって原始的じゃない?」と言われて愕然としたことがあります。彼らにとっては、神社は単なる観光スポットや建築物でしかなく、その場所に対する「畏れ」や「敬意」という感覚が根本的に異なるのです。
情報不足と伝わりにくさ
また、訪日前に適切な情報を得る機会が少ないことも要因です。多言語での情報提供は増えていますが、「なぜそれがダメなのか」という理由や背景まで十分に伝わっていないケースが多いのです。
先日、私が外国人観光客に「手水舎ではこうするんですよ」と教えたら、「ありがとう!ガイドブックには載ってなかった!」と喜ばれました。知らないだけで、教えてもらえたら理解して尊重してくれる人も多いのです。
SNS時代の承認欲求
そして見逃せないのは、SNSの影響です。「いいね」や注目を集めるために、より過激な行動や写真を求める風潮があります。鳥居でのダンスや、禁止区域での撮影など、SNS映えを狙った行為が多いのも特徴です。
友人がこう言っていました。「みくちゃん、正直言うと、私も海外で『映える』写真撮りたくて、あまり考えずに行動したことある。自分も気をつけなきゃなって思う…」
これは私たち日本人も無縁ではない問題かもしれません。

Part 4:未来のために、今できること
神社の尊厳を守りながら、異文化交流を進めるためには、どうすればいいのでしょうか?
多角的なアプローチ
表2:神社での「不敬行為」対策アクションプラン
| 対策カテゴリ | 具体的なアクション例 | 期待される効果 | 考えられる課題・留意点 |
|---|---|---|---|
| ① 情報提供の強化 | ・多言語での分かりやすいマナーガイド作成・配布<br>・理由や背景を説明<br>・動画やインフォグラフィック活用<br>・旅行会社・ガイドへの情報提供・研修 | 事前の理解促進、誤解の防止、納得感の向上 | 情報が届かない層、言語対応の限界、情報過多にならない工夫、継続的な更新 |
| ② 環境整備 | ・分かりやすいピクトグラム(絵文字)の設置<br>・多言語での注意喚起サイン設置<br>・立ち入り禁止区域の物理的障壁強化<br>・手水舎の作法イラスト表示<br>・ゴミ箱設置・清掃体制強化 | 言葉の壁を超えた注意喚起、物理的な抑止、快適な環境維持 | 景観との調和、設置場所の選定、ピクトグラムのデザイン統一性、維持管理コスト |
| ③ 人的対応の強化 | ・多言語対応可能なスタッフ・ボランティアの配置<br>・巡回・声かけの強化<br>・地域住民との連携による見守り<br>・トラブル発生時の対応マニュアル整備 | 直接的な注意・説明、早期発見・対応、地域一体での取り組み | 人材確保・育成、人件費、ボランティアの負担、声かけの難しさ、地域住民との合意形成 |
| ④ 啓発・教育 | ・SNSでのマナー啓発キャンペーン<br>・インフルエンサーとの連携<br>・学校教育での異文化理解・マナー教育<br>・メディアでの継続的な情報発信 | 幅広い層への意識向上、長期的な価値観の醸成、国内外での理解促進 | 情報の届き方の偏り、一方的な押し付けにならない工夫、効果測定の難しさ |
| ⑤ ルール・規制 | ・悪質な行為に対する罰則の検討・明確化<br>・入場制限や予約制導入の検討<br>・特定の撮影行為の禁止区域設定 | 抑止力の向上、オーバーツーリズム対策、神聖な空間の保護 | 法整備のハードル、観光客の反発、運用ルールの複雑化、「おもてなし」との両立 |
| ⑥ 技術の活用 | ・翻訳アプリ・ツールの活用<br>・マナー学習アプリの開発<br>・AIカメラによる迷惑行為検知(研究段階)<br>・VR等での事前学習体験 | コミュニケーション補助、効率的な情報提供、新たな注意喚起手法、体験を通じた理解促進 | 技術導入コスト、プライバシーへの配慮、誤検知のリスク、技術への過信禁物 |
私が注目したいのは、特に「情報提供」と「教育」の部分です。先日訪れた京都の神社では、おみくじの箱の横に「This is not a toy. Please treat with respect.(これはおもちゃではありません。敬意を持って扱ってください)」という手書きの札が置かれていました。シンプルですが、「なぜそうすべきか」が伝わる工夫をしていて感動しました。
一人ひとりができること
私たち一人ひとりにもできることがあります。
- 日本の文化や神社の意味について、改めて学ぶ
- 外国人観光客が困っていたら、優しく教えてあげる
- 海外旅行の際は、その国のルールを事前に調べ、尊重する
- SNSへの投稿が、誰かを傷つけたり誤解を招いたりしないか考える
この記事を書きながら、私自身も「私は海外で失礼なことをしていないだろうか」と考えさせられました。正直、過去の自分の行動を振り返ると反省することもあります。文化の違いを理解し、敬意を持つことの大切さを、改めて実感しています。
まとめ:文化の壁を越えて、共に生きるために
この問題は、単なる「観光マナー」にとどまらず、異なる文化を持つ人々がどう尊重し合い、共存していくかという大きなテーマです。
神社の「悲鳴」を聞いていると、日本の大切な文化が失われていくことへの不安と悲しみを感じます。しかし同時に、多くの外国人観光客は日本の文化に敬意を持って接しようとしていることも忘れてはいけません。
対立するのではなく、相互理解を深めていく。それが最も大切なことなのではないでしょうか。
取材を終えて私が最も心に残ったのは、ある古くからある神社の宮司さんの言葉です。
「神社は千年以上も様々な困難を乗り越えてきました。時代が変わっても、神様と人とを繋ぐ場所としての本質は変わりません。これからも丁寧に伝えていくことで、きっと理解してもらえると信じています」
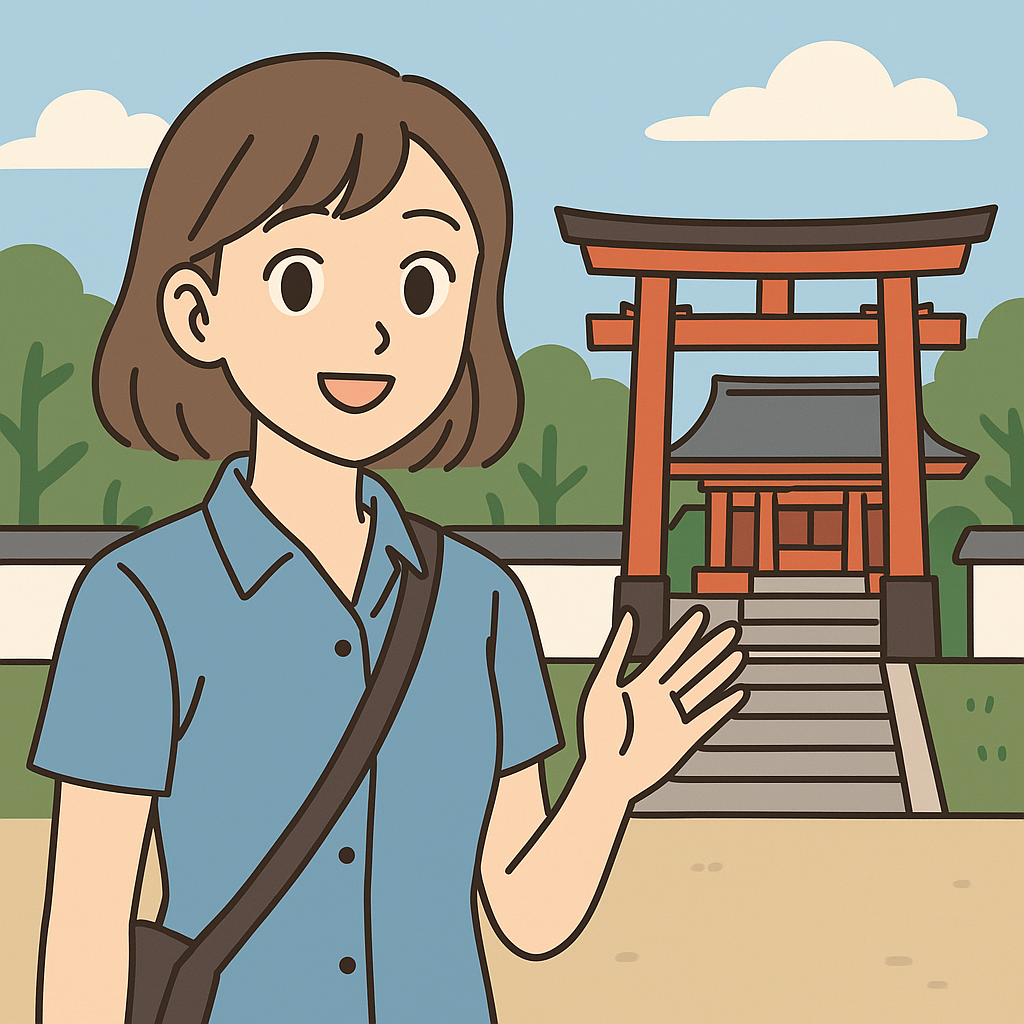
この言葉に、希望と覚悟を感じました。
私たちにできることは、日本の文化の価値を再認識し、多様性を受け入れながら、未来につなげていくこと。それは決して簡単ではないけれど、避けては通れない道だと思います。
皆さんは、この問題について、どう思いますか?コメントで意見を聞かせてください。
長い記事を最後まで読んでくださり、ありがとうございました。この記事が、異文化理解や尊重について考えるきっかけになれば幸いです。
※※関連記事※※
文化庁:宗教文化の理解に向けて
日本政府観光局(JNTO):訪日外国人向けマナー情報
神社本庁:神社の作法とマナー
#神社マナー #おみくじガチャ #外国人観光客 #文化衝突 #インバウンド問題 #日本文化を守る #観光マナー #宗教リテラシー #不敬行為 #共生社会

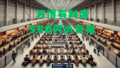
コメント